感情のマネジメントはビジネスに必須!実務で活かせる3つのメリット
いつも怒っていて接しづらい。不愛想で何を考えているのかわからない。あなたの職場にもこんな人はいませんか?
実はこうした人たちは感情のマネジメントができていないせいで、周囲とのコミュニケーションに問題が生じているのです。
組織では人との交流は避けられません。どうしたらこのような人物と打ち解けられるのか、また自分は周囲から同じように見られていないか、気になる方もいるでしょう。
そこで今回はビジネスに必須とされる感情のマネジメントについて、実務で活かせる3つのメリットをご紹介します。
目次
 感情のマネジメントって?ビジネスシーンと結びつく理由とは
感情のマネジメントって?ビジネスシーンと結びつく理由とは

感情のマネジメントとは何か。一言でいえば自分または周囲の感情をコントロールして、成果を出すための考え方です。感情的な人物は組織において調和を乱し、またその人物の役職が上になるほど部下は委縮するといいますが、その関連性をみていきましょう。
1. 感情的な人材は組織で使いにくい?
仕事ができないわけではないのに評価に結びつかない。そんな人は少なくありません。あなたの上司・部下、もしくはあなた自身もそうかもしれませんね。
- 能力が高いもののすぐに怒りやすい
- 経験豊富だが自分の考えに固執する
- 論理的な思考を相手に押し付けてくる
こうした傾向はコミュニケーションが不慣れな人によく見られ、感情をコントロールできないことから生じています。感情的な人材は組織で使いにくいのです。
2. ビジネスシーンと感情のマネジメントの密接性
組織では伝える力が重視されますが、例えばプロジェクトリーダーがキレやすく落ち着きのない衝動的な人物であると、周囲は委縮して意見をすることが難しくなってしまいます。それは問題提起や課題解決プロセスの障壁となるでしょう。
誰かが感情を周囲にぶつけ、その結果周囲が感情を抑え込むことになっている。こうした構図に気が付くことができるかどうかが感情のマネジメントの分かれ道です。チームのモチベーションを上げ、組織全体の感情をコントロールすることが成果につながります。
 感情のマネジメントは社会人で活きる!3つのメリットを理解しよう
感情のマネジメントは社会人で活きる!3つのメリットを理解しよう

感情のマネジメントがもたらす3つのメリットをご紹介します。感情をコントロールすることで情報共有がスムーズになり、こころの健康も保たれ、事業にもプラスに働くといいますから、それぞれの内容をチェックしていきましょう。
1. 組織のスムーズな情報共有が可能に
誰もが落ち着いて意見しやすい雰囲気づくりによって、上からも下からも意見を集約しやすい環境が実現できるでしょう。怒られるかも…という感情はマイナスにしか働きません。
トップダウンでは意見の吸い上げが極端に減り、現場の問題がトップまで届いていないことも珍しくないといいます。誰でも気軽に意見を発せられる状況を作りましょう。
2. メンタルヘルスケアでQOL向上!
ストレスの多い現代社会ではメンタルヘルス、つまりこころの健康状態を高く維持することが重要です。心が軽い・穏やかな気持ち・やる気が沸いてくる、こうした気持ちを維持することは、組織全体の活力や生産性に多大な影響を及ぼすことがわかっています。
またメンタルヘルスが維持されれば、生活の質であるQOL(=Quality of Life)も向上するでしょう。仕事での満足度は身体的な苦痛の軽減・社会的活動を含めた活力・生きがい、といった形で私生活にまで影響します。ライフワークバランスの観点でも調和した生活が実現できるでしょう。
3. 感情に訴えかける商品・サービス展開も
感情のマネジメントができるようになると、人を動かす力について学ぶようになります。つまり周囲に気持ちよく動いてもらうためにはどうすべきかを考えるため、自然とどんな感情を引き起こせばよいかという視点を持つのです。
これは社内統治だけでなくBtoCのビジネスにおいても重要な観点で、顧客に自社の商品やサービスをどう訴求していくか、思わず手に取りたくなるようなあおり文句など、感情に訴えかける戦略を考えることにもつながります。
 感情のマネジメントを実践!シチュエーション別に事例をチェック
感情のマネジメントを実践!シチュエーション別に事例をチェック

感情をマネジメントするには、どんな場面でどのような行動をとればよいのでしょうか。代表的な3つのシチュエーションから、その実践例をご紹介します。自分と周囲のコミュニケーションの質を高めるため、感情をうまく活用しましょう。
1. 感情を言語化して周囲と打ち解けよう
コミュニケーションがうまい人は自分の感情を言語化する能力に長けています。思ったことを言葉にすると自分の考えを伝えられるだけでなく、周囲に自分がどのような人物かを適切に伝えられるようになるでしょう。
そうしたやりとりを相互に行うと周囲とも関係性を築きやすくなります。何を考えているのかわからない、という人には中々近寄りがたいものです。チームを組んでまもない状況などでは、周囲と打ち解けるために感情を積極的に言語化しましょう。
2. 感情を引き出すならボディランゲージ
自分が積極的にコミュニケーションを取ろうとしているのに、周囲がそれに合わせてくれない。と感じることはありませんか?そのような場合は「見た目から」相手の感情を引き出しやすくする雰囲気作りが重要です。
そこでボディランゲージを使うとより効果的。人は相手の動きからも感情を読み取ろうとします。いくら友好的な会話の内容でも、見るからにイライラしていそうな相手には意見しづらいでしょう。ゆっくり動く、腕組みしない、相手を真似るミラーリングなど手段も豊富。
3. アンガーマネジメントで叱り上手に
問題が発生した場合、組織の中で叱咤激励しなければならないことも多いでしょう。しかし感情的になって怒鳴りつけるのは間違いです。相手の感情にとってみれば叱ることがメインと取られかねず、問題を解決したいという当初の目的とは離れていってしまうのです。
そこでアンガーマネジメントの考え方が注目されています。怒りの感情は6秒以上続かないとされますから、まずは落ち着いて思考できるように努めましょう。また自分自身は何に怒っているのか、そして怒りやすいのか、そのパターンを把握するとより効果的です。
まとめ
今回はビジネスに必須といわれる感情のマネジメントについて、実務でも使える3つのメリットをご紹介しました。人間は感情で動く生き物ですから、コントロールできればパフォーマンスの向上が期待できます。
また自分だけでなく周囲の感情をマネジメントできるようになると、組織全体のパフォーマンス向上にもつながるでしょう。
周囲のモチベーションを上げつつ成果を出したいという方は、一度感情のマネジメントについて考えてみるといいかもしれません。
——————————————
弊社が運営する、「リカレントビジネス・カレッジ 基礎編」では、すぐにビジネスに活用できるビジネススキル・非認知能力をワークショップ形式で体験し、学べることができます。
そんな非認知能力・ビジネススキルを短期間で上げられる講座にご興味があれば、下記のボタンから基礎コースの詳細とお申込詳細をご覧ください。
そんなワークショップを運営するトレーナーたちが、どのような思いで、どんなふうにこのプログラムを運営しているのか?また、トレーナーたちはこれまでの成功体験と失敗体験から、どのようにして非認知能力を養っていったのか?ぜひ、こちらからご覧ください。
そして、参加者が講座に参加した後、今まで仕事・ビジネスがうまくいかない原因を突き止めて、そこから独立起業を一気に進めました。
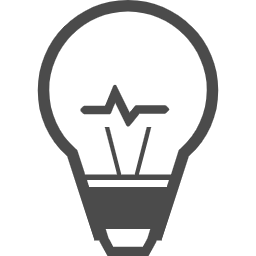 感情のマネジメントって?ビジネスシーンと結びつく理由とは
感情のマネジメントって?ビジネスシーンと結びつく理由とは